幅広い心理学のテーマの中で、『学習・認知・知覚心理学』は、永続的な行動の変容をもたらす「学習」、そのために自分の周りの物事が見える・聞こえるといった「知覚」、それについて理解し、記憶する「認知」を学ぶものです。
本記事では、この「学習・認知・知覚心理学」を構成するそれぞれの領域について紹介します。
学習・認知・知覚

本テーマでは、永続的な行動の変容をもたらす「学習」、そのために自分の周りの物事が見える・聞こえるといった「知覚」、それについて理解し、記憶する「認知」を扱います。
- 学習心理学
- 認知心理学
- 知覚心理学
以下、それぞれの領域における主なポイントを紹介します。
学習心理学
古典的条件づけ
パヴロフが発見した、「イヌに音を鳴らした後に餌を与え続けると、イヌは音を聞いただけで唾液を分泌するようになる」学習過程を『古典的条件づけ(レスポンデント条件づけ)』と呼びます。
この例では、『餌』は、条件づけをしなくても生得的に『唾液分泌(無条件反応(UR))』を引き起こす無条件刺激(US)となります。
音は初め餌とは無関係な中性刺激でしたが、条件づけにより餌を予告する条件刺激(CS)となり、音による唾液分泌が条件反応(CR)となります。
オペラント条件づけ
生体はさまざまな行動(オペラント)を自発し、行動がもたらした結果によって次の行動が変化、この学習過程を『オペラント条件づけ(道具的条件づけ)』といいます。
反応に随伴して餌などの強化刺激を与える手続きを強化と呼び、条件づけは以下の4つに分類できます。
- 正の強化 … 反応すれば報酬を与えると、反応が増加する
- 正の罰 … 反応すれば嫌悪刺激を与えると、反応が減少する
- 負の罰 … 反応すれば報酬を除去すると、反応が減少する
- 負の強化 … 反応すれば嫌悪刺激を除去すると、反応が増加する
認知心理学
記憶の区分
「記憶」は、情報を頭の中に入れ(符号化)、情報を一定期間保持し(貯蔵)、必要に応じて情報を想い出す(検索)過程です。
記憶を時間で区分すると、以下の二重(多重)貯蔵庫モデルになります。
- 感覚記憶 … 瞬間的にほぼすべての情報を保持できるが、保持時間は一秒程度
- 短期記憶 … 15~30秒ほど保持、一部リハーサルによって長期貯蔵庫に転送
- 長期記憶 … 数分間から数年間、一生にわたって保持(エピソード記憶、意味記憶、手続き記憶など)
短期貯蔵庫では、情報の保持だけではなく、情報を処理する『ワーキングメモリ』の概念もあります。
記憶と感情
感情によって、記憶も影響を受け、快でも不快でも、感情(情動)が喚起された情報は、喚起されない情報よりも想起されやすいです。
また以下の効果のように、情報を記銘するときの気分が記憶に影響すると言われています。
- 気分状態依存効果 … 覚えるときと想い出すときの文脈が一致している場合が、一致していない場合よりも再生率が高くなる現象
- 気分一致効果 … 参加者の気分に一致する内容の記憶が想起される現象
パターン認識
パターン認識をする際、『トップアップ処理』と『ボトムアップ処理』の2つが行われています。
知覚心理学
視覚の知覚
視知覚は、網膜上の視細胞(錐体と桿体)が光を感知し、視交叉を経て、後頭葉領域(一次視覚野)に伝達されます。
特に、3次元性の知覚を「奥行き知覚」と呼びます。
網膜は、2次元的構造であるため、脳は奥行き情報を再現するために手がかりとして、『両眼性手がかり(両眼視差、輻輳)』、『単眼性手がかり(調節、絵画的手がかり)』を利用しています。
運動の知覚
運動の知覚は、対象が物理的に運動している場合(実際運動)だけでなく、実際には運動していない(仮現運動)対象に対しても生じます。
特に『仮現運動』は、さらに以下のような運動に分類できます。
- 誘導運動 … 視野内に静止した対象と移動する対象が同時に存在するとき、静止した対象が移動するように知覚される現象
- 運動残効 … 一定方向に運動する対象を長時間観察した後に、静止対象に逆流性の運動が知覚される現象
- 自動運動 … 暗闇の中に静止した光点を提示すると、次第に光点が浮遊しているかのように知覚される運動
聴覚の知覚
聴覚は、空気の振動によって引き起こされる音の感覚で、鼓膜に到達した音波が、内耳にある蝸牛において電気信号に変換、内側膝状体を経て側頭葉にある一次聴覚野へ送られます。
ある感覚様相の知覚が他の感覚様相の知覚によって影響を受ける現象を『クロスモーダル知覚』と呼び、特に「腹話術効果」や「マガーク効果」が有名です。
まとめ
本記事では、永続的な行動の変容をもたらす「学習」、そのために自分の周りの物事が見える・聞こえるといった「知覚」、それについて理解し、記憶する「認知」を学ぶ『学習・認知・知覚』のエッセンスについてまとめてみました。
興味を持たれた方は、書籍などでさらに学ばれることをオススメします。
以下の記事にて、心理学検定について詳しくまとめていますので、ご興味あれば合わせてお読みください。

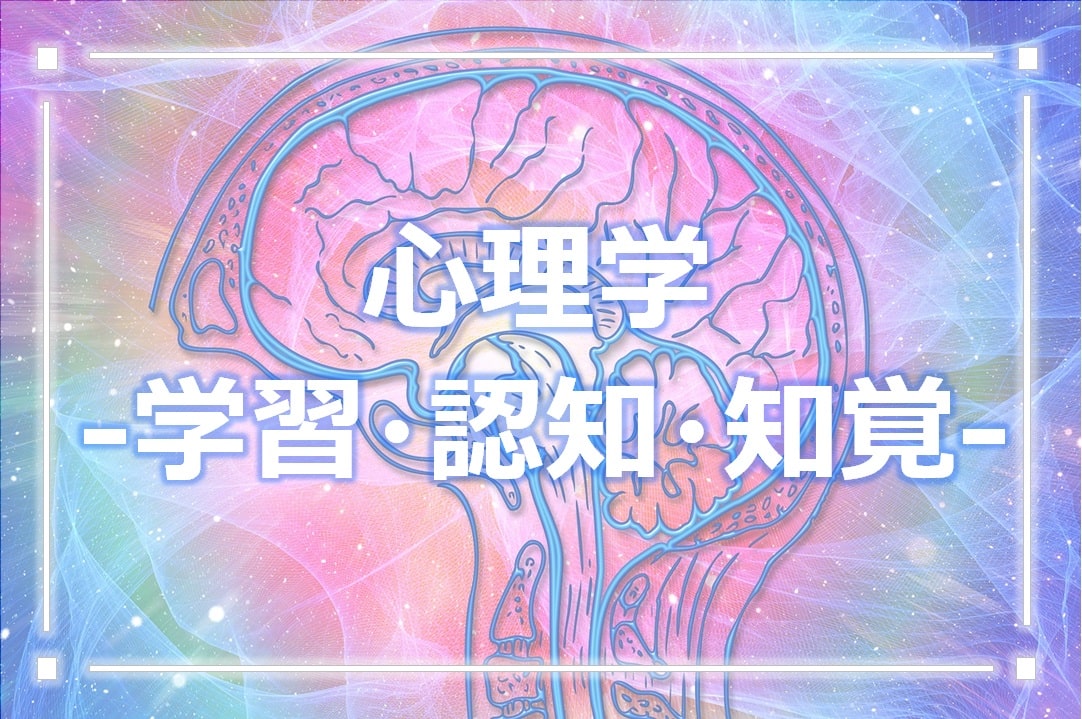
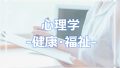

コメント