今現在、幸せに生活していたとしても、この先のことは誰にもわかりません。
もしもの際に家族を困らせないために、不慮のアクシデントの場合にご家族に残される生活の『不足額』を把握する必要があります。
本記事を読みながら、ご自身のケースにおける『不足額』を算出してみましょう。
なぜ『不足額』を知ることが重要?
今回は、妻子を持った夫が急逝してしまった仮定をモデルケースとして、その際に生じる『不足額』を以下のように「支出」と「収入」から算出します。
.jpg)

『不足額』を求めることに何の意味があるのか、と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
『不足額』を求めるのは、ご自身にもしもの事があった場合にこれから必要となる「支出」と、ご家族への「収入」を正しく理解し、不足が生じないよう今のうちに対策を打つための現状把握です。
支出
「支出」については、日々の生活にかかる『生活費』と、子どもの教育や冠婚葬祭にかかる『別途必要資金』に分けて考えましょう。
生活費

生活費の算出に当たっては、「子が独立するまで」と「子が独立後(母の一人暮らし)」の2つのフェーズに分類して考える必要があります。
生活費(母の一人暮らし)= 27万円/月 × 0.5 × 12カ月 ≒ 162万円/年
別途必要資金

教育費
『教育費』は、子どもが幼稚園・保育園から大学まで通うために発生する費用です。
それぞれ、国公立に通うのか、私立に通うのかで大きく異なってくる数値ですが、一般的なモデルケースとして幼稚園・保育園から高校までを公立、大学を私立に通った場合で一人当たり『約1000万円』と言われています。
冠婚葬祭費
『冠婚葬祭費』は、ご自身の葬儀代や、子どもの結婚祝いの支出です。
本モデルケースでは、冠婚葬祭費を以下のように算出します。
予備費
『予備費』は、一定の決まりはなく、不測の事態などに対し発生する費用です。
例えば、残された妻が病気などで働けなくなった場合でも数年間生活できる資金、などの観点で考えるとよいでしょう。
収入
「収入」については、ご自身の死亡に対する遺族年金や遺族の老後の老齢年金など継続的に受給する『年金』と、ご自身の死亡時に資産として相続される『自己資産・企業保障』に分けて考えましょう。
年金

『年金』の算出に当たっては、下記の3つの受給時期に分類して考える必要があります。
| Phase | 受給時期 | 受給可能な年金 |
| Phase-1 | ~子が18歳 | ①遺族厚生年金 + ②遺族基礎年金 |
| Phase-2 | 子が19歳~妻が65歳まで | ①遺族厚生年金 + ③中高齢寡婦加算 |
| Phase-3 | 妻が65歳~ | ①遺族厚生年金 + ④妻の老齢基礎年金 |
-1024x455.jpg)
① 遺族厚生年金
①遺族厚生年金は、主たる生計者が死亡した場合の、労働者の遺族に対する生活保障で、妻や子の年齢に関わらず継続的に支給される年金、支給額は以下となります。
※ ただし、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなし計算
ご自身が現時点で死亡した際の、遺族厚生年金の算出の基となる老齢厚生年金額は、日本年金機構の『ねんきんネット』から確認ができます。
・”合計期間の詳細”の「(A)一般厚生年金被保険者 加入期間」
・”これまでの加入実績に応じた年金見込額の情報”の「(B)老齢厚生年金額」
遺族厚生年金額は以下で算出できます
(A)加入期間≧300月の場合:(B)老齢厚生年金額 × 3/4
(A)加入期間<300月の場合:(B)老齢厚生年金額 × 300月/(A)加入期間× 3/4
② 遺族基礎年金
②遺族基礎年金は、主たる生計者が死亡した場合の、遺族に対する生活保障で、以下の遺族が受給対象となります。
- 18歳未満の(または20歳未満で一定障害がある)子ども
- 上記に該当する子どもと生計を同じにする配偶者
つまり、遺族基礎年金の支給は子どもが18歳になるまでとなります。
遺族基礎年金の基本額は『780,900円× 改定率』、子どもの数に応じ下記が加算されます。
| 1人目・2人目 | 224,700円× 改定率(1人あたり) |
| 3人目以降 | 74,900円× 改定率(1人あたり) |
③ 中高齢寡婦加算
③中高齢寡婦加算は、「妻が40歳に達したとき(40歳以後に夫が死亡した場合そのとき)から65歳までの期間」に(子どもが18歳以上などのため)遺族基礎年金が受給できない際、妻のみに支給される遺族厚生年金の加算です。
中高齢寡婦加算の支給額は、『遺族基礎年金額 × 3/4』となります。
④ 妻の老齢基礎年金
妻が受給する予定の老齢基礎年金(+老齢厚生年金)は、日本年金機構の『ねんきんネット』から確認ができます(将来の年金額を試算より)。
-min-160x90.jpg)
自己資産・企業保障

『自己資産』はご自身の預貯金や、現金化可能な有価証券などを指します。
また、『企業保障』として、死亡時の死亡退職金などが発生する場合は、確実に盛り込んでおきましょう。
不足額

これまでに算出した「支出」と「収入」の差分を計算し、『不足額』が明らかになりました。
数千万円という数字を見るとショックを受けてしまうかもしれませんが、この『不足額』を明らかにし、どのような手段で不足額をゼロにするか検討することが不足額算出の目的です。
例えば、残された妻がパートタイムなどで働き、年間100万円の収入を20年続けることで、単純計算で「2,000万円」の収入となります。
そうすると、残りの「2,500万円」は生命保険への加入で補償しよう、など具体的な施策が打てるようになります。
今回のように、公的補償や必要資金を精査した上で適切な対策を打ちましょう。
まとめ
本記事では、ご自身の不慮のアクシデントの場合にご家族に残される生活『不足額』の算出についてご紹介しました。
前述の通り、『不足額』を明らかにすることで、不足額をゼロにするための手段を検討することが目的です。
手段については本記事では取り扱いませんが、主たる手段となる生命保険については、下記書籍などでその役割などを理解し、ご自身に合った保険に加入されることをオススメします。
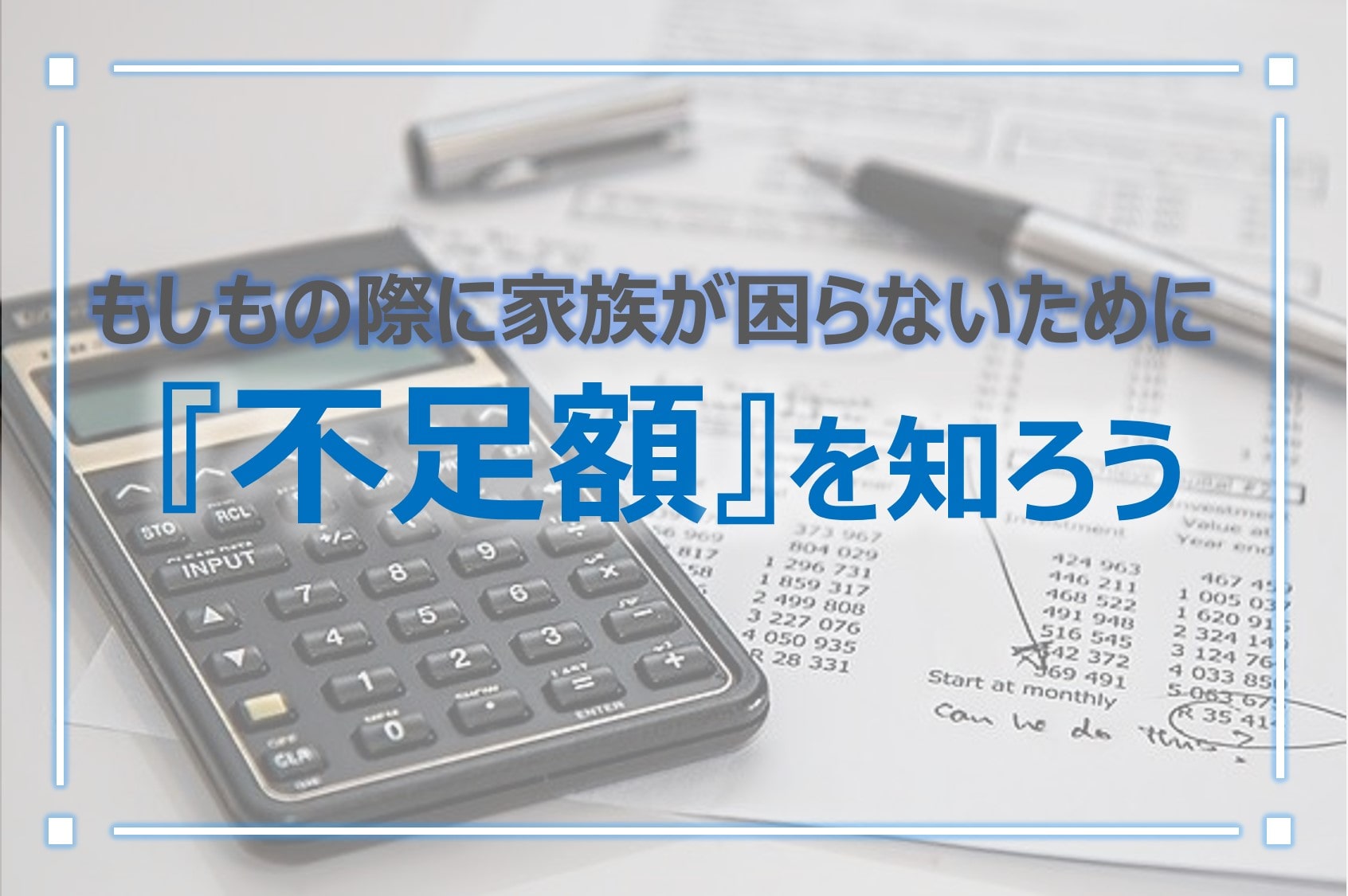


コメント