中小企業診断士試験の勉強をしていると、今勉強している内容が合格後どう役に立つの?実際に使う機会があるの?と考えてしまうこともありますよね。
今回は、中小企業診断士試験に向けて勉強する試験科目と実務との関連や、お役立ち度について紹介します。ぜひご自身試験勉強のモチベーションアップにつなげてください。
企業経営理論・財務会計・運営管理編はこちら
経営情報システム (実務お役立ち度:B)
経営情報システムは、中小企業診断士試験としては一次試験の一科目、二次試験とも関連性は高くない科目ですが実務では相当に必要とされます。現在の企業経営においてITや情報の扱いは切ってもきれない関係にあるためです。
特に現在の中小企業は、ビッグデータを使いこなす若手ベンチャーから、パソコンも扱えない老舗事業主とITリテラシーが二分しており、特に後者のクライアントに対してのIT化というのは中小企業診断士に求められる役割となります。
ITリテラシーは個人個人でも相当に異なるものとなるため、かなりハイレベルなコンサルティングからExcelで帳簿管理を行えるようにする、というところまで実務の内容は多岐にわたります。

そういった中小企業に「Excelでの帳簿管理による業務効率化」や「インターネット上のWebサイト構築による受注経路拡大」をするというのは立派なコンサルティングですし、実際に経営情報システムの範囲で行うコンサルティング業務はこちらがメインになります。
さらに昨今ではクラウド化やキャッシュレス化がテーマとなっているため、クラウド人事総務システムやクラウド会計システム、はたまた小売店向けのPOSレジを提案できることは一つの強みです。
これらの分野については詳細仕様や構築方法を知っているというより、モノを知っていて、導入条件やもたらす便益が紹介できる、というのが重要と思います (もちろんあなたの提案で購入を決めたクライアントに対しては実際の導入から、導入効果を感じることができるまでお手伝いしてあげてください)。
中小企業診断士はIT経験者の方も多いので、高度な情報システムのコンサルティングを求められるのであればタッグを組んで進めることをお勧めします。
経済学・経済政策 (実務お役立ち度:C)

経済学・経済政策はマクロ経済、ミクロ経済共にCです。実務で使うことはまずないかと思われます。
とはいえ国の経済動向や景気など、基本は抑えた中小企業診断士となってください、ということですね。
実務というわけではないですが、中小に関わらず事業主の方は例外なく自社を守るため人一倍経済動向や景気には敏感ですので常に最新の動向を抑える必要があると言えます。
経営法務 (実務お役立ち度:C)

経営法務は、経済学・経済政策同様、実務で実務で使うことはまずないかと思われます。大きな理由として、中小企業事業主が経営法務を期待して中小企業診断士へコンサルティングを依頼することはほぼないためです。
この領域の業務は弁護士や司法書士、行政書士、社会保険労務士など国で定められた別の士業がいるわけですからプロにお任せするべきです。
中小企業診断士としてはこれらの士業とのネットワークを持ち、気軽に紹介してあげられるというのが強みになると思います。
とはいえ経済学・経済政策同様、当たり前のことすら知らないようではクライアントの信頼も得られませんので最低限の知識は知っておきましょう、というくらいですね。
中小企業経営・政策 (実務お役立ち度:B)

中小企業経営・政策はAとしたいところですが、そのままの知識が実務につながるわけではないということでBとさせていただきました。
とはいえ「中小企業診断士」が中小企業診断士たるゆえんとなるところなので事業主に対峙するものの知識として当然、というところになりますね。
重要な点として、「中小企業」の感覚を正しく理解しているということが挙げられます。
大企業に勤めながら中小企業診断士になられた方が大企業の感覚で中小企業にコンサルティングする方は多く見受けられます。しかし、大企業と中小企業でとるべき戦略は明らかに異なります。
中小企業は、「本来大企業であれば当然あるアセットが無い状態でどうしていくかというマインド」、というのは頭ではわかっていながらどうしても大企業マインドで接してしまう、そうすると中小事業主の心はすぐに離れてしまいます(私自身その経験があります)。
また中小企業経営・政策分野の実務としては、国の補助金の申請コンサルティングが多いです。そのため今現在どういった方々に対して何の補助金が存在するのか、その条件は何か、といったことを中小企業診断士になってから常に追いかけ続けましょう。
まとめ
これまで述べてきたように、中小企業診断士試験の試験科目はいずれも実務においても役に立つものとなります。
ぜひ試験勉強の際は実務を意識し、ご自身が中小企業診断士としてクライアントに接していると思いながら勉強してみましょう。習得度が段違いとなるはずです。
本記事は後編となります。前編記事はこちら!
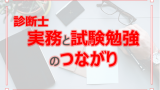
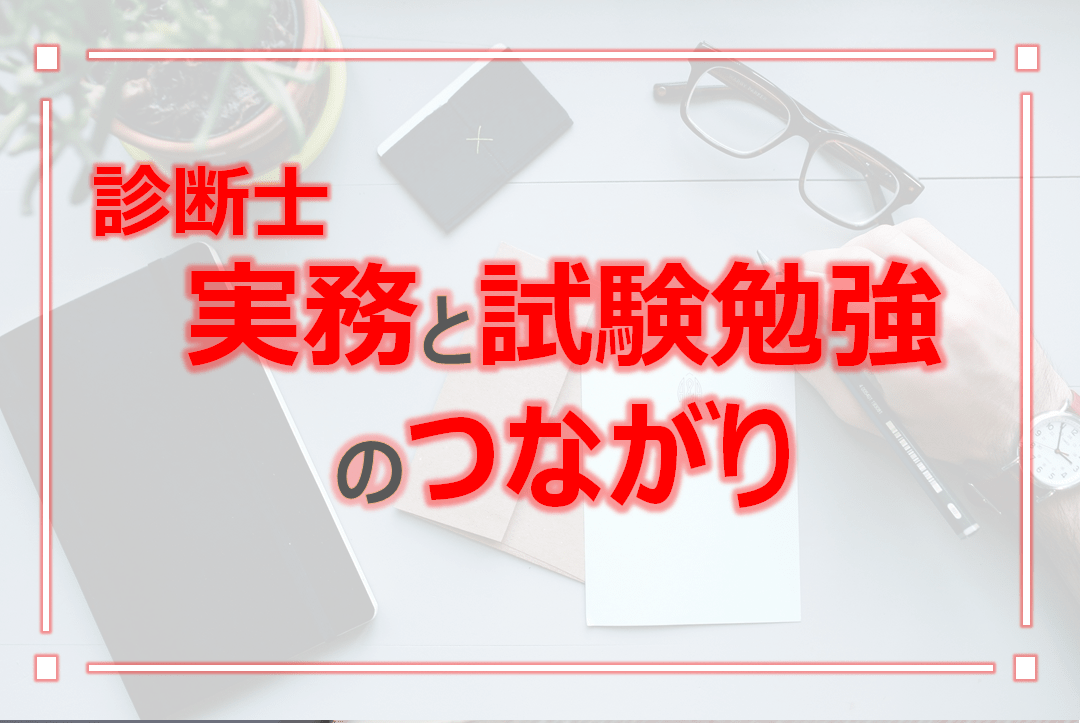


コメント