幅広い心理学のテーマの中で、『神経・生理心理学』は、脳内の神経伝達物質や神経内分泌系、心臓血管系の活動といった、定量的な指標をこころの現れを扱う領域です。
本記事では、この「神経・生理心理学」を構成するそれぞれの領域について紹介します。
神経・生理

本テーマでは、脳内の神経伝達物質や神経内分泌系、心臓血管系の活動といった、定量的な指標をこころの現れとして扱う「神経・生理」を扱います。
- 神経心理学
- 生理心理学
以下、それぞれの領域における主なポイントを紹介します。
脳の構造と機能
中脳・小脳
特に、『延髄』・『橋』・『中脳』をまとめて脳幹といいます。
中脳には、視覚に関与する『上丘』と、聴覚に関与する『下丘』があります。
小脳は、「運動機能の統合」や「姿勢反射」を主な機能しますが、最近では高次脳機能の役割も注目されています。
大脳
大脳は、以下の領域から構成されます。
- 後頭葉 … 一次視覚野を含む領域
- 頭頂葉 … 一次感覚野を含む領域
- 前頭葉… 一次運動野を含む領域
- 側頭葉 … 一次聴覚野を含む領域
ブローカは、左の大脳半球の前頭葉前部皮質の下側部の領域が言語算出の中心である『ブローカ野』、一方で左側頭葉一時聴覚野の後側に言語理解の領域である『ウェルニッケ野』を主張しました。
神経細胞の構造と機能
神経細胞(ニューロン)と神経伝達物質
ヒトの脳の神経細胞(ニューロン)は、脳全体の細胞数に対し10%を占めています(残りの90%はグリア細胞)。
神経細胞間のコミュニケーションは、『シナプス』という構造を介して行われます。
「電気シナプス」と「化学シナプス」の2種類から構成され、特に「化学シナプス」は、神経終末から信号物質(神経伝達物質)が放出、もう一方の細胞が膜の受容体を介して受け取るというものです。
主な神経伝達物質は以下のように分類できます。
| アミノ酸 | グルタミン酸 | 興奮性のシナプス |
| γ-アミノ酪酸(GABA) | 抑制性のシナプス | |
| アミン | アセチルコリン | 運動神経・副交感神経の神経伝達物質 |
| ドーパミン | 動機づけにかかわる報酬系 | |
| セロトニン | 覚醒と関係する | |
| ペプチド | バソプレッシン | 社会行割動に重要な役割 |
| オキシトシン | ||
| オレキシン | 睡眠・覚醒に深くかかわり |
自律神経系機能
神経系は「中枢神経系」と「末梢神経系」に、「末梢神経系」はさらに「体性神経系」と「自律神経系」に分類されます。
また、「自律神経系」は以下の2つに分類されます。
| 交感神経 | 胸髄と腰髄から出ている | ノルアドレナリンやアドレナリンを分泌 |
| 副交感神経 | 脳幹と仙髄から出ている | アセチルコリンを分泌 |
生理心理・精神生理
遺伝子
髪の形状や瞳の色といった形質が親から子へと伝わる現象を『遺伝』、それを発現するもとになるのが『遺伝子』です。
遺伝子は、二重らせん構造の「デオキシリボ核酸(DNA)分子」と「ヒストン・タンパク」からなる染色体に存在します。
2本鎖DNAが1本鎖となりRNAが結合し『メッセンジャーRNA(mRNA)』となり(転写)、mRNAからタンパクが作られます(翻訳)。
感情の機能
感情に関する機能は、その考え方により下記のように複数の理論が展開されています。
- ジェームズ = ランゲ説(感情の末梢説) … 刺激によって喚起された生理反応が感情体験を引き起こす(泣くから悲しい)
- キャノン = バード説(感情の中枢説)… 身体反応と並行して感情は生じる(悲しいから泣く)
- シャクター = シンガー説(認知覚醒理論)… 感情の2要因理論
睡眠と覚醒
睡眠は、その深さから、以下のように5段階に分類されます。
| レム | 低振幅の脳波と素早い眼球運動が特徴 | |
| ノンレム | 段階1 | (アルファ波やベータ波は消失し) 低振幅速波やシータ波が現れ、ゆっくりとした眼球運動(SEM)が観察 |
| 段階2 | 睡眠紡錘波やK複合波が観察 | |
| 段階3 | デルタ波が20~30%未満見られる | |
| 段階4 | デルタ波が50%以上を占める | |
睡眠の調整機構は複雑ですが、代表的な神経伝達物質として『メラトニン』や『オレキシン』がかかわります。
まとめ
本記事では、脳内の神経伝達物質や神経内分泌系、心臓血管系の活動といった、定量的な指標をこころの現れとして扱う『神経・生理』のエッセンスについてまとめてみました。
興味を持たれた方は、書籍などでさらに学ばれることをオススメします。
以下の記事にて、心理学検定について詳しくまとめていますので、ご興味あれば合わせてお読みください。

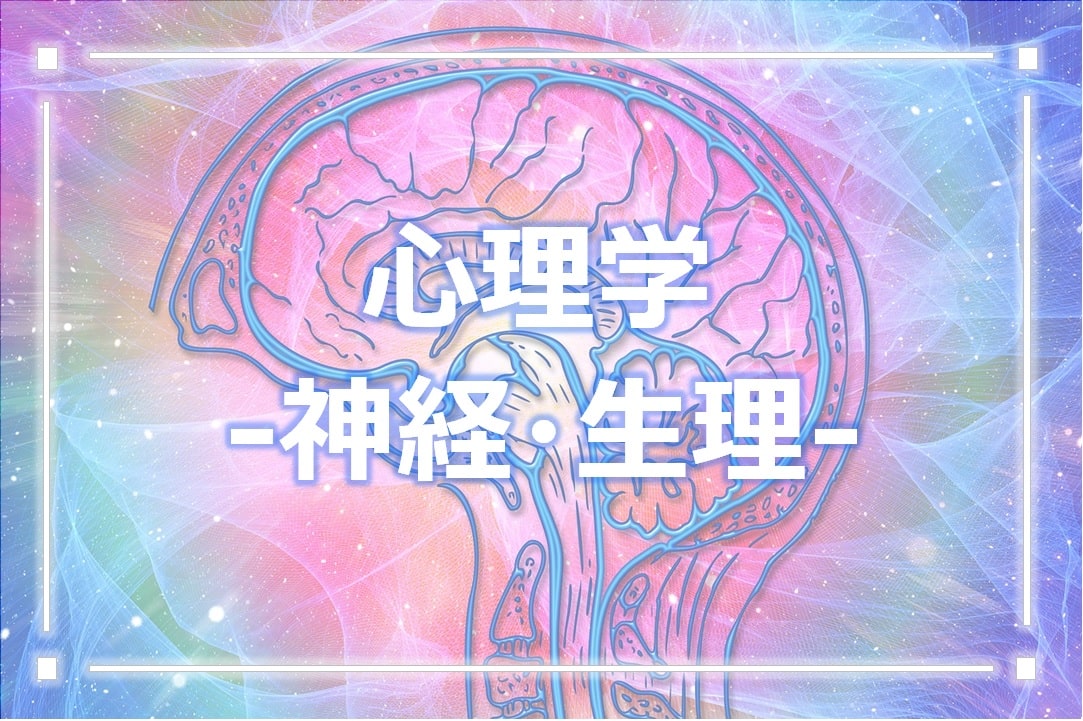


コメント