皆さんは、ビジネスにおいてリサーチが必要となった際、どのように行っていますか?
多くの方は、まず可能な限り多くの情報を収集し、一通り目を通した上で、その後アウトプットを思考し、纏めるのではないでしょうか。
今回は、ビジネス現場(特にコンサルティング現場)で使えるリサーチ手法についてご紹介します。
リサーチにおける3つのプロセス

リサーチを行う際は、冒頭に紹介したように、フォアキャスティングではなく、バックキャスティング(最初に目標を描き、それを実現するためのプロセスを未来から現在へさかのぼるシナリオ手法)の考え方が重要です。
実際には、下記の3ステップでリサーチを行うことになりますが、『実行』前の『定義』や『設計』がリサーチ成功のカギとなります。
- リサーチの定義(目的の明確化)
- リサーチの設計(手段の明確化)
- リサーチの実行(アウトプット)
以下、それぞれのフェーズにおけるポイントを紹介します。
リサーチの定義(目的の明確化)
リサーチを行う場合、どう調べるのか『設計』し『実行』するという2ステップで行われがちで、何を調べるのかの『定義』が疎かになることが少なくありませんが、実際のリサーチにおいてはこのフェーズが最も重要と言っても過言ではありません。
リサーチの目的確認
多くの場合、リサーチの目的は「新しい知識を得る」ことではないはずです。
リサーチの最初の段階で、「リサーチを通して何の課題を解決したいのか」を明確にしなければいけません。
目的と手段を取り違えることなく、まずは『目的』を明確化しましょう。
リサーチのレベル確認
リサーチの目的と同様に重要な視点は、リサーチの『レベル』を定義すること、『レベル』は以下の3つから構成されます。
| スピード | リサーチにかける時間(1時間?1日?1週間?1カ月?) |
| 広さ | リサーチの網羅性(対象領域のみ?周辺領域まで含める?他領域まで調査?) |
| 深さ | リサーチの精度(公知の情報?複数の情報ソースによる検証?個別ヒアリング?) |
特にチームでリサーチを行う場合、レベルが共通認識となっていないとバラバラのアウトプットとなってしまいます。
リサーチの設計(手段の明確化)
リサーチの『実行』に着手する前に、「どの情報源に、どの順番でリサーチするか」という設計が必要です。
リサーチはやみくもに取り掛かるのではなく「仮説」を立て、仮説検証のために情報源をどう活用するか、設計するようにしましょう。
リサーチの情報源設計
リサーチの『目的』と『レベル』が定義されると、次はどの情報源にあたるかを設計します。
下記のように、リサーチするタイプにより適する手法は異なります。
常識・トレンドを素早く知る
| Web | インターネット検索を用いた情報収集 |
| 文献 | 書籍(基本書・専門書)や媒体(新聞・雑誌)による情報収集 |
体系化された全体像を知る
| 統計・レポート | 公的(行政・研究機関)や民間(調査会社)の報告による情報収集 |
| アンケート | アンケートによる情報収集 |
常識・トレンドを素早く知る
| ソーシャルリスニング | 消費者のSNS発信による情報収集 |
| フィールド調査 | 現場の体験・観察による情報収集 |
| インタビュー | 有識者への問いかけによる情報収集 |
リサーチの順序設計
情報源に対しどの順序でリサーチするかについて、以下のような留意点があります。
浅い情報→深い情報の順序でリサーチ
複数の情報源を用いる場合、Webなどの「浅い情報」からリサーチを始め、その後統計・レポートやインタビューなどの「深い情報」へアクセスすべきです。
「浅い情報」へアクセスすることで常識や全体像を短期間でつかむことができ、リサーチ対象に対し理解や仮説を持った上で「深い情報」に触れることができるためです。
直列ではなく並行で複数の情報源へリサーチ
一つの情報源に頼ると、本来アクセスしたかった情報にアクセスできないリスクがあります。
そのため、例えば統計・レポートを用いる場合にも複数選択肢を用意しておきましょう。
また、インタビューなど、実際に情報取得までにリードタイムを要するものについては前もって動くスケジューリングを組みましょう。
仮説が外れた際の対応策を考慮
リサーチに先立って仮説設定の重要性を解きましたが、実際のリサーチにおいて仮説が外れることは珍しくありません。
この場合、最初からリサーチをし直すことにならないよう、一定程度の幅広さを持ったリサーチ設計としておきましょう。
リサーチの実行(アウトプット)
リサーチを『定義』、『設計』し、ようやく『実行』に着手します。
一見遠回りのようですが、『定義』、『設計』ができていることで、効率よく、効果的に『実行』することができます。
リサーチの実行
リサーチの実行においては、アクセスしやすい「浅い情報」であるほど、単体では価値が無いことがほとんどです。
そのため、意味のあるリサーチを行うのであれば、価値を高めるため、希少価値の高い「深い情報」へアクセスする、または複数の情報を組み合わせメッセージ性を出すといった差別化が必要となります。
リサーチのアウトプット
リサーチ結果は、最終的にプレゼン資料へアウトプットされることが多いですが、前段にExcel等で情報整理することをオススメします。
その際、以下のようなポイントをおさえましょう。
- 内容はもちろんのこと、「情報鮮度」、「出典」についても記載する
- リサーチした「事実」と「私見」を分けて整理する
情報整理後、そこから得られる知見を最終アウトプットにまとめます。
最終的なプレゼン資料へのアウトプットのポイントは、以下記事にまとめていますので、ご興味あれば合わせてお読みください。

まとめ
ビジネス現場(特にコンサルティング現場)で使えるリサーチ手法についてご紹介しました。
記事内でご紹介したように、バックキャスティング思考(目的を達成するための手段としてのリサーチ)を心掛けましょう。
次ステップとしてリサーチの具体的なアプローチを理解したい場合、下記記事を合わせてお読みください。

リサーチスキルを上げるには実践が一番ですが、まずは手法を深く学びたいという方は、下記の『外資系コンサルのリサーチ技法』が大変オススメです。
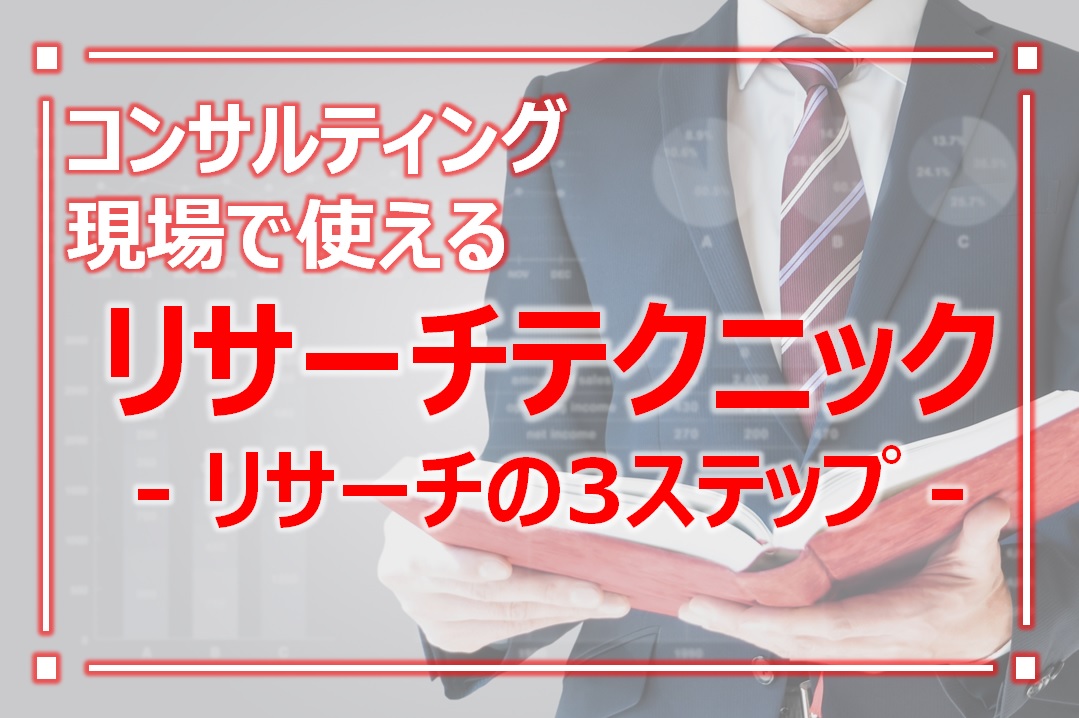


コメント