幅広い心理学のテーマの中で、『臨床・障害心理学』は、カウンセリングや心理療法などの心理臨床と、こころの病や障害をまとめた学問です。
本記事では、この「臨床・障害心理学」を構成するそれぞれの領域について紹介します。
臨床・障害

「臨床・障害」は、カウンセリングや心理療法などの心理臨床と、こころの病や障害をまとめた学問で、、下記のテーマから構成されます。
- 精神分析
- 行動主義
- 心理学的アセスメント
- 精神疾患・病理
以下、それぞれの領域における主なポイントを紹介します。
精神分析
精神分析療法と心的装置論
「精神分析療法」は、創始者であるフロイトとその後継者の精神療法で、自由連想法を創出し、『抵抗』、『転換』、『転移』などの基礎概念を明らかにしました。
フロイトが心的現象理解のために提起した心のモデル(心的装置)では、心を以下の3層構造に定義しました。
- 自我 … 外界を知覚し自己概念やわたくし意識に関するもの
- エス(イド) … 無意識の内容物
- 超自我 … 自我に関する監視役(幼児期に心の中に取り込まれた親のイメージ)
分析心理学
ユングは、「分析心理学」を創始した、フロイトの後継者です。
ユングは無意識を2層に分け、『個人的無意識』と『普遍的無意識』と仮定、特に後者を個人の心の根底で人類に共通して伝承された主題である「元型」としました。
行動主義
行動療法
「行動療法」は、学習理論に基づいて人間の問題行動を変容させる方法です。
学習には、『レスポンデント条件づけ』、『オペラント条件づけ』、『社会的学習』の3タイプがあります。
レスポンデント条件づけ
特定の人や物・場所に、明確な理由なく不安や恐怖を感じる場合、『レスポンデント条件づけ』が働いている可能性があります。
このような場合、「リラクセーション反応」や「系統的脱感作法」、「エクスポージャー(曝露法)」といった学習方法による不安や恐怖の抑制が用いられます。
オペラント条件づけ
『オペラント条件づけ』は、1つの行動を「先行条件-行動-結果の枠組み(三項随伴性)」でとらえます。
特定の行動に対して好子や嫌子を伴わせることで、行動の生起頻度を変化させます。
- 正の強化 … 好子出現の強化(生起頻度の増加)
- 負の強化 … 嫌子出現の強化(生起頻度の増加)
- 負の弱化 … 嫌子出現の弱化(生起頻度の減少)
- 正の弱化 … 好子出現の弱化(生起頻度の減少)
オペラント条件づけは、「トークンエコノミー法」や「シェイピング」に用いられます。
社会的学習
『社会的学習』の中心となるのは、バンデューラによる「観察学習(モデリング)」、自分自身が直接経験せずとも、他者(モデル)の行動・結果を観察することが新しい行動の取得に繋がるという発見です。
自律訓練法
シュルツの『自律訓練法』は、催眠と同じ状態を得るための生理的かつ合理的な練習法です。
背景公式と第1~6公式の言語公式から構成されます。
- 第1公式 … 四肢重感練習
- 第2公式 … 四肢温感練習
- 第3公式 … 心臓調整練習
- 第4公式 … 呼吸調整練習
- 第5公式 … 腹部温感練習
- 第6公式 … 額部涼感練習
心理学的アセスメント
心理検査
心理学的アセスメントの一つである心理検査には、性格検査・知能検査・発達検査・適性検査など多くが存在します。
性格検査は、その理論的背景によって3つに大別されます。
- 投影法 … ロールシャッハテスト、TAT、バウムテスト、HTPテスト、SCT、P-Fスタディ
- 質問紙法 … MPI、EPPS、エゴグラム、MMPI、YG性格検査
- 作業検査法 … 内田クレペリン検査、IAT
これらの性格検査は一長一短あるため、複数性格検査の組み合わせ(テストバッテリー)が重要です。
また知能検査においても、さまざまな種類がありますが、特に『ビネー式知能検査』と『ウェイクスラー知能検査』が有名です。
各国で翻訳改訂されており、米国ターマンによる「スタンフォード・ビネー法」、我が国では田中寛一による「田中ビネー法」が有名です。
幼児用の「WPPSI」、児童用の「WISC」、成人用の「WAIS」が有名です。
精神疾患・病理
DSM(操作的診断基準)
精神疾患のための診断・統計マニュアルとして『DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)』が操作的診断基準として定められています。
2013年にDSM-5が発表、DSM-Ⅳから大きく改訂された主な内容は以下となります。
- 広汎性発達障害(自閉症やアスペルガー障害を下位分類)を、自閉スペクトラム症(ASD)と定義
- 気分障害の下位分類であった双極性障害群と抑うつ障害群を、独立した新カテゴリーに分類
子どもの発達障害
発達障害者支援法において、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害」と定義されています。
米国の精神医学者カナーによって提出された自閉症概念に端を発し、オーストラリアの小児科医アスペルガーの症例報告を基に、イギリスの精神科医ウィングによって「アスペルガー症候群」として広まりました。
少年院の主たる業務は、家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し「矯正教育」を行うことです。
まとめ
本記事では、カウンセリングや心理療法などの心理臨床と、こころの病や障害をまとめた『臨床・障害』のエッセンスについてまとめてみました。
興味を持たれた方は、書籍などでさらに学ばれることをオススメします。
以下の記事にて、心理学検定について詳しくまとめていますので、ご興味あれば合わせてお読みください。



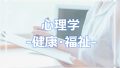
コメント