FP(ファイナンシャルプランナー)試験は、お金全般に関する試験ですが、学習においては各科目の全体像を把握することが重要となります。
今回は、我々が行う資産運用のベースとなる知識となる『金融資産運用』について概要を紹介します。
金融資産運用
『金融資産運用』は、マクロ観点から景気や物価を捉える「経済」や経済を回すため国として行う「金融政策」、ミクロ観点で個々の「金融商品」について学びます。
-min.jpg)
以下、それぞれの項目について概要を紹介します。
経済指標
お金について考える際、マクロ観点から経済や景気の状況を捉える必要があります。
以下では、基本として抑えておくべき経済指標を紹介します。
GDP(国内総生産)・GDE(国内総支出)
GDP(国内総生産)は、内閣府が年4回公表する、1年間に国内で生産されたモノ・サービスの付加価値の総額です(GDPは国の経済規模を示す指標で、日本はGDP世界第3位)。
GDE(国内総支出)は、GDPが生産面から見た指標であるのに対し、支出面から見た指標です。
日銀短観
『日銀短観』は、日銀(日本銀行)が行っている、企業の経済活動の現状把握・将来予測のための調査です。
業況判断DI(ディフュージョン・インデックス)の数値が上昇すると景気拡大局面、下落すると景気縮小局面にいると見なされます。
景気動向指数
『景気動向指数』は、内閣府が毎月公表する、景気の動きを客観的に把握するための指標で、下記の3系列から構成されます。
| 系列 | 特徴 | 指標例(雇用関連指標) |
| 先行系列 | 景気に先行して動く指標 | 新規求人数 |
| 一致系列 | 景気と同じタイミングで動く指標 | 有効求人倍率 |
| 遅行系列 | 景気に遅れて動く指標指標 | 完全失業率 |
金融政策
金融市場
『金融』とはお金の流通であり、お金が流通する場所を「金融市場」と言います。
金融市場は、下記のように大きく取引期間で短期と長期に分類されます。
| 金融市場 | 短期 (1年未満の取引) | インターバンク (金融機関のみ参加可) |
| オープン市場 (一般事業法人も参加可) | ||
| 長期 (1年以上の取引) | 公社債市場 | |
| 株式市場 |
金利は、短期的には日本銀行の金融政策によって水準が決まりますが、長期的には下記のように景気・物価・為替などによって変動します。
| 長期金利 | ||
| 国内景気 | 好況 | ↑ |
| 不況 | ↓ | |
| 国内物価 | 上昇 | ↑ |
| 下落 | ↓ | |
| 為替相場 | 円安 | ↑ |
| 円高 | ↓ | |
| 海外金利 | 上昇 | ↑ |
| 低下 | ↓ | |
金融政策
日本の中央銀行である日本銀行は、物価の安定などを目標とし様々な『金融政策』を実施しています。
主な金融政策である『公開市場操作』は、日本銀行が景気により国債などを売買し、マネーストック(市場に流通する通貨量)を調整する政策です。
-1024x642.jpg)
金融商品
金融商品は、預貯金を代表とする『貯蓄型金融商品』と、債券・株式・投資信託などの『投資型金融資産』に分類できます。
預貯金
『預金』や『貯金』は、銀行などの金融機関にお金を預けるもので、金融機関が元本・利子の支払を保証しているため安全性が高い商品です。
債券
『債券』は国・企業が資金調達のため発行する証券、下記が決められ発行されます。
| 表面利率 | 額面金額に対する利子の割合 |
| 発行価格 | 新発債を発行する際の売出価格 |
| 償還期限 | 債券の額面金額が償還される期日 |
債券では、『利回り(債券投資で得られる収益を投資金額で割ったもの)』の考え方が重要です。
債券の収益は、インカムゲイン(投資に対する利子収入)と、キャピタルゲイン(償還・譲渡の利益)があります。
②最終利回り
③所有期間利回り
④直接利回り
-1024x684.jpg)
上記の例では、インカムゲイン = 1万円、キャピタルゲイン ≒ 0.25万円 、利回り=1.25%と算出することができます。
株式
『株式』は、株式会社が資金調達のために発行する証券です。
他の金融商品と異なり、株式保有者は、会社の株主となり、経営参加権などの権利があるのが特徴です。
株式市場の動向を捉えるために、下記のような代表的な株価指数を抑える必要があります。
| 日経平均株価 (日系225) | 東証1部に上場している代表的な225銘柄の平均株価 |
| TOPIX (東証株価指数) | 東証1部に上場している全銘柄の平均株価 |
株式投資の収益は、インカムゲイン(株式保有による配当金)と、キャピタルゲイン(売買による譲渡益)があります。
株式銘柄を選択する際には、下記のような指標にて割安性などを分析します(ファンダメンタルズ分析)。
| PER (株価収益率) | 株価/1株当たり純利益 |
| PBR (株価純資産倍率) | 株価/1株当たり純資産 |
| 配当利回り | 配当金/株価 |
| 配当性向 | 配当金/1株当たり純利益 |
| ROE (自己資本利益率) | 当期純利益/自己資本 |
投資信託
『投資信託』は、複数の投資家から資金を集め、投資専門家(ファンドマネージャー)が債券・株式などに分散投資、利益を投資家に分配するしくみの金融商品です。
複数の商品によるリスクを抑えた分散投資が投資信託のメリットです。
投資信託は、下記の運用スタイルで分類することができます。
| パッシブ運用 | TOPIXなどのベンチマーク連動を目的とする投資信託 |
| アクティブ運用 | ベンチマークを上回る運用収益を目指す投資信託 |
外貨建て金融商品
『外貨建て金融商品』とは、外貨(米ドルやユーロなど)で運用する金融商品で、外貨預金、外国債券、外国株式、外国為替投資などがあります。
外貨建て金融商品の特徴は、為替リスクを有することです。
購入時と比較し為替レートが円安に推移すると為替差益を得ることが出来ますが、一方で円高に振れると為替差損を被ります。
.jpg)
金融商品の税金
金融商品の利子や配当には、商品ごとに税金(所得税+住民税)が課せられます。
| 金融商品 | 種類 | 所得 | 税率 | 課税方式 |
| 預貯金 (含 外貨預金) | 利子 | 利子所得 | 20.315% | 源泉分離課税 |
| 為替差益 | 雑所得 | 総合課税 | ||
| 債券 (含 公社債投資信託) | 利子 | 利子所得 | 申告分離課税 | |
| 譲渡益 | 譲渡所得 | 申告分離課税 | ||
| 株式 (含 株式投資信託) | 配当 | 配当所得 | 源泉徴収 | |
| 譲渡益 | 譲渡所得 | 申告分離課税 |
まとめ
今回は『金融資産運用』について紹介しました。
FP試験では多彩なしくみや制度を学ぶため、計算方法や制度詳細にフォーカスしてしまいがちですが、しくみや制度の位置づけや全体像を把握することが重要になります。
試験勉強のフェーズにかかわらず、下記のような入門本に立ち返ってみるのもオススメです。
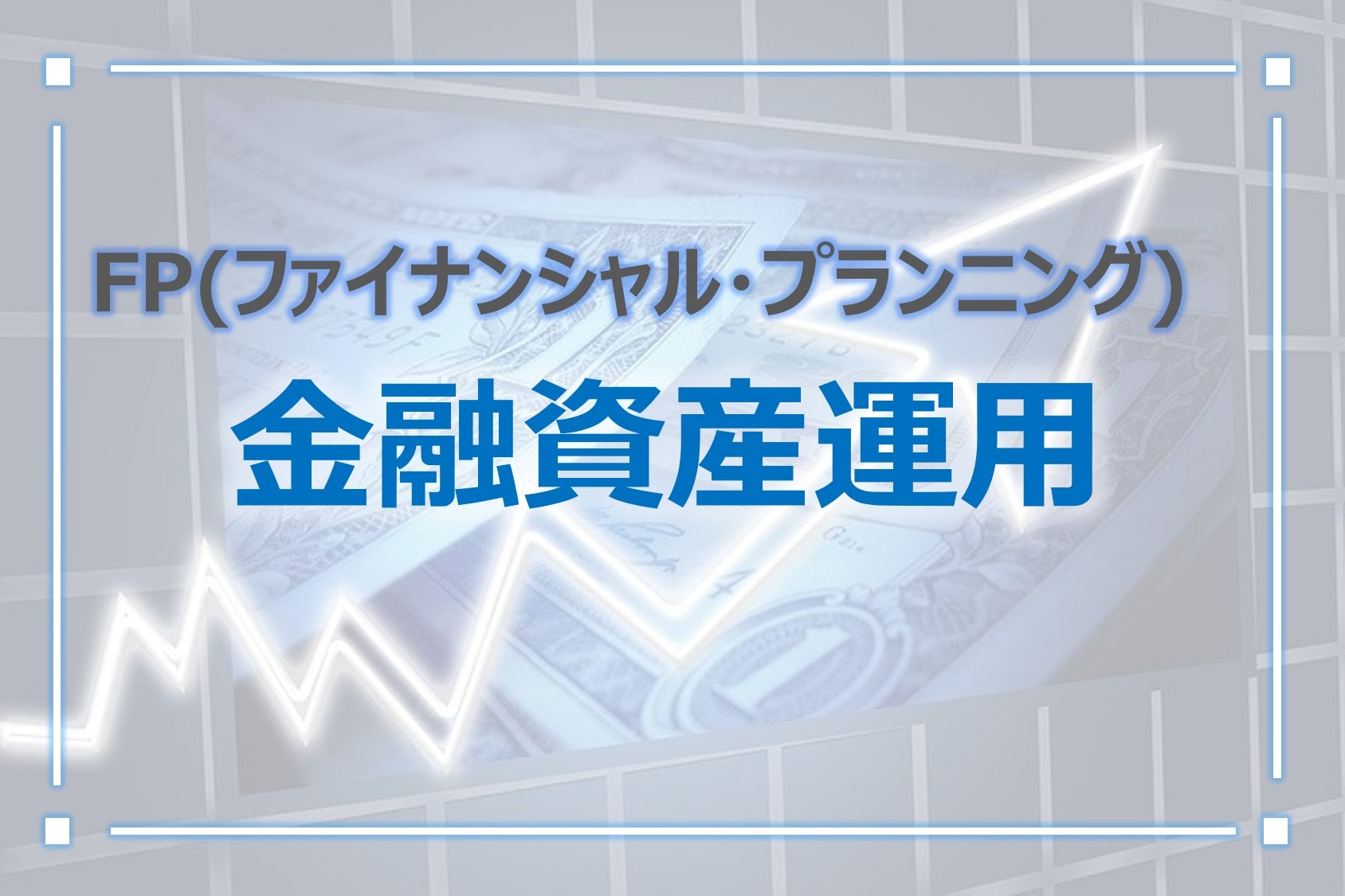


コメント