中小企業診断士試験合格に必要と言われている学習時間は、およそ1,000時間です。いくらモチベーションが高くてもテキストや問題集とにらめっこし続けるのは肉体的にも精神的にも疲れますよね。
せっかくの長い道のりですので、試験合格だけを目的にするのではなく、日常生活や会社生活の中で学んでいる知識がどう活かされているか考え、また感じてみてはいかがでしょうか?
一見遠回りなことをしているようにも見えますが、結果的に試験学習にも活かされてきます。
中小企業診断士試験学習は日常や会社生活の中で使われている
冒頭の通り、中小企業診断士試験で学ぶ内容は、皆さんの日常や会社生活の中で様々使われています。
そのため、長い中小企業診断士試験に向けた学習を、テキストや問題集を解くためだけの時間とせず、日常や会社生活の中でリンクさせてみることをお勧めします。それには大きな2つのメリットがあります。
- 会社での評価につながる
- 試験学習の知識定着になる
メリット① 会社での評価につながる

ひとつめのメリットは、会社でのご自身の評価アップにつながることです。
中小企業診断士で学習する内容は、企業経営理論や財務・会計など企業活動で必須となる理論です。裏を返すと、(当たり前のことではありますが)企業活動では中小企業診断士で学習する内容を活かすチャンスであふれているということです。
この事実は、中小企業診断士の学習を始めるまでは意識をしないこともあり見落とされがちです。上司やお客との議論の際に学習で学んだフレームワークを活用するだけで、周囲のあなたへの見る目が変わるでしょう。
メリット② 試験学習の知識定着になる
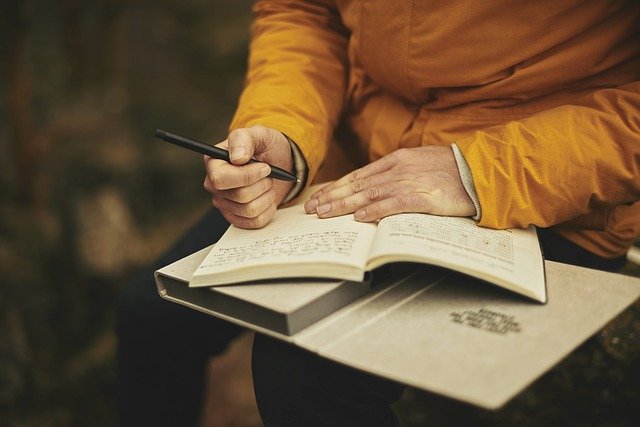
ふたつめのメリットは、実際に使ってみた・触れてみたことが試験学習の深い知識定着に結びつくことです。
中小企業診断士試験の学習は理論中心となるため机上ではイメージがつきにくいことが非常に多いので、結果的に身をもって理論を活用した取り組みに触れる機会を作ることで知識定着の度合いが各段に違います。
日常や会社生活で触れる事例
企業経営理論
企業経営理論は企業活動と特に強い紐づきがあります。
会社員の皆さんであれば、おそらく他の科目と比較して学習時にピンとこないということは少ないのではないでしょうか。
自社の中期経営戦略を調べてみると、「これは多角化戦略だ」、「今自分が担当している製品は製品ライフサイクルのどのあたりだろうか」、など中小企業診断士学習を始める前と比較して見え方が違ってくると思います。

さらに前述のように、上司やお客との議論や提案の際に、企業経営理論のSWOT、PEST、5フォースなどのフレームワークをどんどん使うようにしましょう。
優秀なフレームワークだからこそ理論化されているわけですからよりよい議論や提案になりますし、また上司やお客のあなたへの見る目も変わります。
財務・会計
企業経営理論同様、財務・会計は企業活動と特に強い紐づきがあります。
会社員の皆さんであれば、ファイナンス分野は経営企画部門や財務部門でもなければ触れる機会は薄いかもしれませんが、アカウンティング分野は誰にも関係が深い、理解しているべき内容となります。
オススメはご自身が務められている会社の経営分析です。

皆さんは自社の『決算』をしっかりと観られたことがありますでしょうか?
- 営業利益や当期純利益は黒字か?
- 自社の「収益性」、「安全性」、「生産性」は同業他社と比較して低くないか?
- 健全なキャッシュフロー経営ができているか?
おそらく上記の問い、一番上は答えられても下二つは答えられない方が多いのではないでしょうか。実際私の周囲でも、業績の良し悪しはなんとなく把握していても自社の営業利益がいくらか、その要因は何かなど把握していない方はかなり多いです。
また上記の問いは自社の決算発表を読み解くことで把握することができます。飲み屋でなんとなく『ウチの会社は今年も厳しいんだよ』とグチを言うだけの存在にならず、同じグチをいうならば経営分析まで語れるようになってみましょう。
運営管理
運営管理は、流通業の店舗勤務の方や生産業の工場勤務の方でないと、なかなか触れる機会が無いと思われるかと思いますがそんなことはありません。
特に店舗・販売管理の店舗管理、誰にとっても身近な日常の中で学ぶことができます。そう、最寄りの『コンビニエンスストア』や『スーパーマーケット』です。
コンビニやスーパーは、中小企業診断士学習で学習する店舗管理手法が十二分に使われています。それを意識してコンビニやスーパーへ行くとこれまでと異なる風景を見ることができ、感動すら覚えます。
いかがでしょうか。コンビニやスーパーに行くだけで店舗管理のエッセンスを生で感じることができるのです。

一方、生産管理の方はさすがにコンビニやスーパーほど身近ではありませんが、ぜひ行っていただきたいのが『工場見学』です。

生産管理は店舗管理と比較して身近でないため、テキストを読んだだけではイメージがつきにくいです。そのため生産現場を生で触れることは相当に学習の理解につなげることができます。
まとめ
本記事で紹介したように、中小企業診断士試験で学習する内容は、皆さんの会社生活や日々の生活の中で登場する知識が本当に多いです。試験勉強の息抜き、かつ理解を深めるためにも日常や会社生活とのリンクを意識すると楽しみながら試験勉強ができると思います。
また日常や会社生活とのリンクで身に着けた内容はご自身が中小企業診断士になった後に実際にクライアントにコンサルティングする場においても多大に活用できますので頑張ってください!
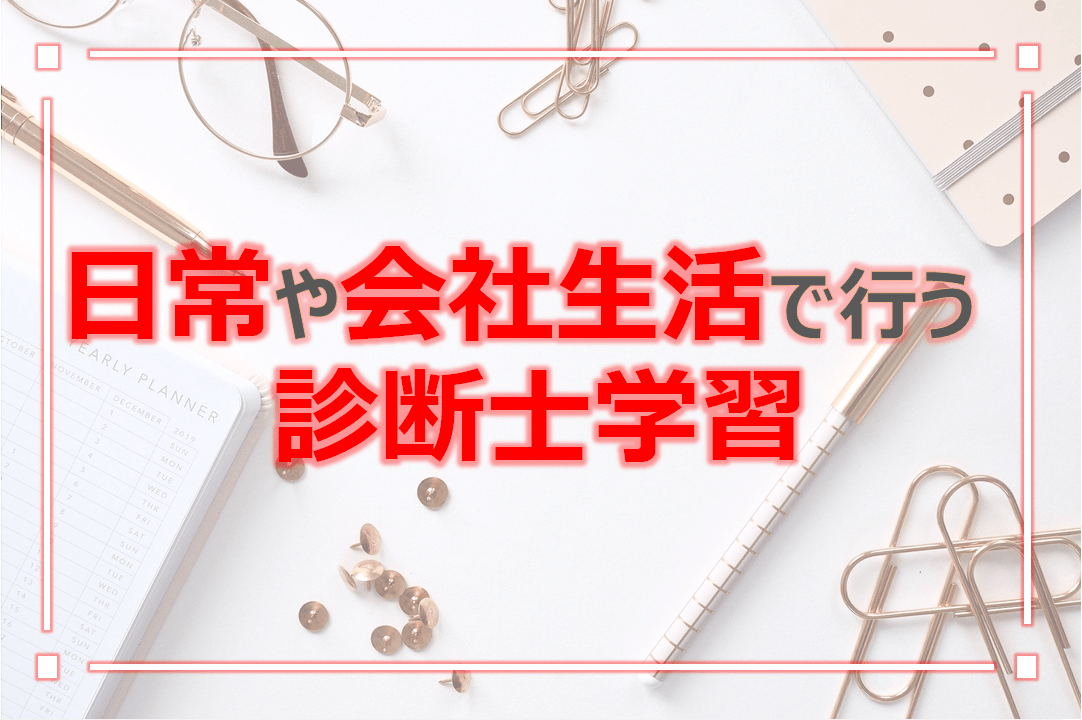


コメント